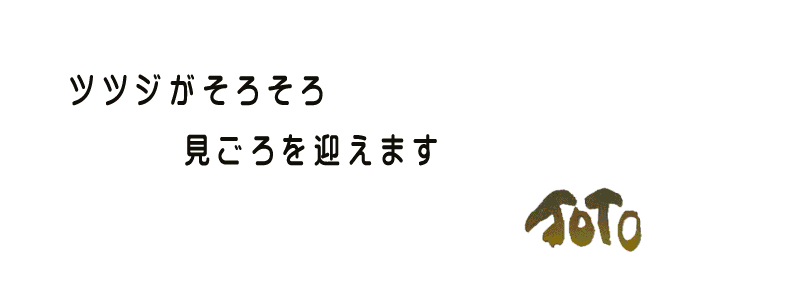
部集会
4月23日を中心日に、部集会が行われています。自己紹介を行ったり、活動方針、今後の予定を確認したりしています。この集会をもって、1年次生の活動が、本格的に始まる部も多いと思います。昨年度の部活動加入率は90%を超えており、部活動が盛んなことが、城東高校の大きな特徴の一つです。「集中と切り替え」を合言葉に、勉学と部活動に全力を注いでいます。そんな2、3年次生を目標に、1年次生は頑張ってもらいたいです。2、3年次生も、憧れの先輩として、様々な活動に励んでほしいです。まだまだ、新入部員を募集している部もあるので、迷っている人は、積極的にチャレンジしましょう。

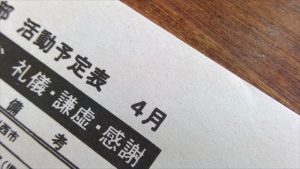
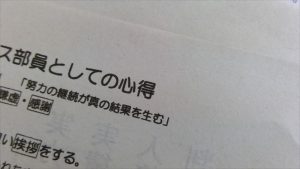


平成30年度岡山県春季高校テニス大会本選
先週の予選に続き、岡山県春季高校テニス大会の本選が、4月20日、21日に県営テニスコートで行われ、女子シングルスに4名、女子ダブルス2ペアが参加しました。シングルスは、全員初戦敗退という結果になりましたが、県上位の選手との高いレベルのテニスを経験することができました。ダブルスでは、竹原さん(3年)、溝渕さん(3年)ペアが、3位に入賞しました。本校テニスコートでは、20日に、本選に出場してない選手が、午前、午後を男女で分け、、本戦出場選手に負けない活躍を目指して、練習を行いました。新入生も多く参加してくれ、3、4人のグループに分かれ、2、3年次生が新入生に打ち方をレクチャーしていきました。23日には、部集会を行い、1年次生を加えた新体制で、本格始動していきます。応援よろしくお願いします。




平成30年度岡山県春季高校テニス大会予選
4月14日、15日に、備前テニスセンターで、岡山県春季高校テニス大会の予選が行われました。本校テニス部にとって、新年度最初の公式戦で、6月に行われる県総体の組み合わせに関わる試合です。女子は、ダブルスで2ペア、シングルスで4名が、来週、県営コートで行われる本選出場が決定しました。
今大会で、早速、新入生も出場しました。現在、男女とも新入部員募集中です。部集会は、来週23日ですが、随時見学、体験練習が可能です。初心者大歓迎です。テニス部は、チーム力NO.1をモットーに、男子は、県総体ベスト8、女子は先月、20年ぶりに出場を果たした全国選抜に続いて、インターハイ出場を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。






本校卒業生が受賞作品の書を寄贈
4月10日(火)、本校卒業生(1期)の奥田清光(雅号 奥田雄山)さんが来校され、書をご寄贈いただきました。「馬鬣(ばりゅう)」という題で、昨年、第4回日本美術展に入選されたものです。作風として、勢いを重視されているとお伺いしましたが、圧倒されてしまうほどの迫力が感じられます。

今後、食堂など多くの生徒が鑑賞できる場所に飾らせていただく予定です。奥田さん、すばらしい作品をどうもありがとうございました。
新入生歓迎会 ~ようこそ、32期生!~
生徒会入会式が終わると、新入生歓迎会が行われます。
今年も各部の魅力あるパフォーマンスが繰り広げられました。

放送部制作による学校紹介ムービーも流されました。
一緒に楽しいJOTOライフを送りましょう!

体育館を出たところでは、上級生が花道を作って
出てくる新入生を自分の部に勧誘していました。

生徒会入会式
始業式に続き生徒会入会式が行われました。
生徒会長の秋山君からは、「城東の自由」についての考え方と、歓迎の言葉がありました。新入生代表の西山さんからは、城東性としての自覚を持って、楽しいことにも、大変なことにも全力で取り組みたいと決意の言葉が、ありました。
32期生360名を迎え、2018年度も活気ある生徒会活動になることを期待しています。


始業式~勢揃い~
入学式のあと1年次から3年次まで1,074名が勢揃いして始業式が行われました。

校長は式辞で「幅広い教養を身につけること」と「主体的に行動すること」について話しました。

最後に生徒課から「スマートフォン」と「交通」についての注意がありました。

今日からいよいよ新年度の本格始動です!
入学式~城東生としての第一歩~
4月9日,入学式があり32期生360名が城東生としての第一歩を踏み出しました。
校長は式辞で校訓の「進取・協同」と「城東の自由」について話しました。

校長式辞より(一部抜粋)
ここで、岡山城東高校の精神的支柱となっている、校訓の「進取・協同」と「城東の自由」についてお話しします。
「進取」は、新しいことに積極的に挑戦することを言います。現代社会はかつてないスピードで進化しています。そのような中では、現状維持は後退を意味します。まず社会の変化をしっかり認識し、常に先取りすべく、新しいことに進んでチャレンジしていくことが大切です。
「協同」は、目標の達成のため、様々な立場の人が力を合わせることを言います。実社会でも、新しいことを始めるときには、様々な専門分野の人がチームを組んで、協力して取り組みます。城東には、広い範囲から多彩な個性が集まっています。互いを尊重し、それぞれの持ち味を生かして、助け合い高めあいながら成長し、3年後には世界を視野に、次のステージに踏み出してもらいたいと思います。
また、「城東の自由」は、開校以来、各期の生徒会が連綿と継承している行動の指針で、進取・協同を効率よく具現化する環境条件ともいえます。皆さんは、ここ城東で、多くの選択肢の中から、自分の自由な判断で、友と協力して新しいことにチャレンジできる環境にいます。しかし、自分で自由に判断したことには当然責任が求められます。自由は互いの自由を認め合ってこそ成立するものだからです。これは学校生活に限ったことではありません。皆さんは18歳になれば有権者となり、政治に参加することが求められます。他人の自由を尊重しながらも、最善の決断が下せる正確な判断力を身につけるためにも、他に流されない信念を持ち、何事にも主体的に取組んでいくことを心がけてください。
私たち教職員は、皆さんを自ら考え、自ら行動し、自ら責任が取れる、自律した人間と認めて接します。このような信頼関係のもと、城東の自由は成立しており、城東の教育が展開されています。皆さんは決して城東の自由を履き違えることなく、城東生の自覚をしっかり持って、城東の伝統をさらに発展させてもらいたいと思います。
新入生代表は,溌剌と声高らかに宣誓を行いました。

最後に,1年次団のスタッフが紹介されました。これからともに頑張っていきましょう!

転退任式~会者定離~
4月は出会いと別れの季節。新任式の後は,転退任式がありました。出会いがあれば別れがあるのは世の常。これを「会者定離(えしゃじょうり)」と言います。今年度は,15名の先生が本校を去ることとなり,転退任式でお言葉をいただきました。

退場では2年次生と3年次生が花道を作ります。別れを惜しみ,先生に駆け寄る生徒も多く見られました。


